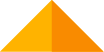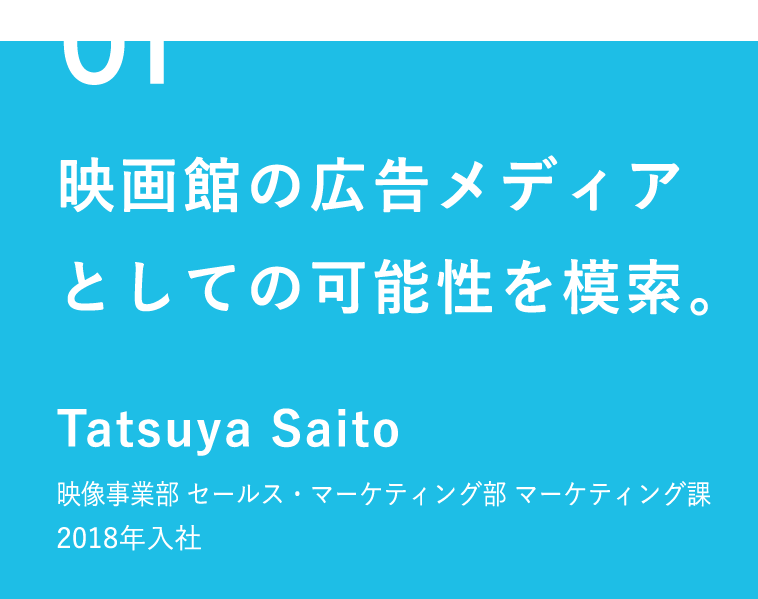

映画や演劇、小説が好きで、大学時代には演劇サークルで脚本などを執筆。就職活動にあたっては「人を楽しませることをしたい」という目標の下、映画・エンターテインメント・映像・マスコミ業界を中心に企業研究を展開。最終的には映画だけでなく多様なエンターテインメント領域をカバーし、新宿や渋谷の再開発事業をはじめ、ダイナミックな動きを推進している東急レクリエーションに魅力を感じ、入社を決意した。

現在の仕事内容について
一言でいうと、映画館内の広告メディアを販売する業務になります。具体的には駅ナカのサイネージ広告や電車のつり革広告などと同じように映画館も広告媒体として活用することができ、館内シアターで本編上映前に放映するCM(シネアド)や劇場に掲示するポスター、さらにはスタッフによるサンプル配布などの広告枠をクライアントに提案・営業するといった仕事です。そうすることで、当社・クライアント・来場者がそれぞれの立場で満足できるような施策を目指しています。たとえば、ある大ヒットアクションシリーズであれば、中高年の男性の間に熱烈なファンが多いといったデータがあるので、その作品が公開される時期に合わせて、ミドル層をターゲットにしたハイブランドの商品を取り扱うクライアントなどに、映画館の広告メディアの提案を行います。また、劇場によって客層が異なる部分もあるので、そのあたりも加味しながら提案を進めるようにしています。気付いている方は少ないかもしれませんが、実は上映作品や劇場によってシネアドの種類は結構違うんですよ。
ちなみに、現部署に配属となったのは2022年7月からで、それまでは3年半ほど当社が直営する小売店のマーチャンダイジング(商品政策)などに携わっていました。その時に磨いてきた「お客様や社会は何を求めているのか」といった視点やマーケティングに関する知見は、今の仕事にも大いに活かされています。
この仕事の難しいところとやりがい
自分の提案が受け入れられ、クライアントから「広告効果があった」という反応をいただけると、心底、うれしくなりますね。そのため、提案を行う際にはクライアントにとっての費用対効果を最大化させるために、クライアントの商品・サービスとの相性、クライアントがどういう層にどうアプローチしていきたいと考えているかといったことを徹底的にリサーチし、提案内容に取り入れるようにしています。
一方で、作品によっては公開直前まで詳細情報が明らかにされないこともあり、クライアントへの説明に困難が生じることがあります。そういった時はその映画のポテンシャルや、公開に合わせて広告を展開することがいかに効果的かを担当者としてどれだけ熱量を持って伝えられるかがポイントになります。その点、もともと映画が好きだったことや映画の知識を持っていることは大きくプラスになっています。もっとも、先輩方のなかにはもっと豊富な知識と熱量を持っている方たちがたくさんいるので、引き続きいろいろと学ばせていただきながら、私自身、クライアントにより良い提案ができるように努めていきたいと考えています。

新しい挑戦
最近力を入れているのが動画配信サービスを展開するクライアントとの連携で、劇場内でシネアドを上映したり、入会促進イベントを行ったりしています。劇場サイドとしては一時期、動画配信サービスの盛り上がりを危惧する考えもありましたが、実際には動画配信サービスでさまざまな作品に接したのを機に映画館に足を運んでくれる来場者が増えており、映画館と動画配信サービスの間にはシナジーがあるということも感じています。しかも、「コト消費」が重視される時代にあって、高品質な映像と音を体感でき、一体感を味わえる映画館という「場」の価値はますます際立ってきており、動画配信サービスから映画館という流れは今後、顕著になってくると思われます。
動画配信サービスに限らず、映画館にはさまざまなメディアやサービスとWin-Winの関係性を構築できる可能性があると思うので、これからもその価値を大切にしながら独自性のある施策を講じていきたいですね。
今後の目標
新たに取り組みたいと思っている施策の一つに「応援広告」というものがあります。いわゆる「推し活」の一環として、広告などを通じて、推しのアイドルやキャラクターを応援するというもので、これをシネアドにも取り入れることができないかと考えています。従来の広告は一般企業がクライアントになるケースが主流でしたが、応援広告となるとSNSを母体としたファングループや個人など一般消費者がクライアントになってくると想定されます。クライアントの幅やシネアドの可能性を広げる上でも非常に有意義だと考えていますし、SNSによる拡散とも親和性が高いと思うので、何とか実現させたいと考えています。また、当社は映画館だけでなく、ボウリング場や小売店など、幅広いレジャー施設を有しているので、私個人としては特に各店舗を繋いだプロモーションを展開してみたいという構想も練っているところです。
私は常々、レクリエーションとは人生における「気晴らし」であると考えています。ちょっと嫌なこと、辛いことがあっても、映画をはじめとしたレクリエーションに接すれば、明日への活力を得ることができるからです。こういったレクリエーションの力を最大限に引き出し、一人でも多くの皆さんの生活を豊かにできるよう、これからも楽しみながら業務に励みたいと思います。
※所属は取材当時のものです。